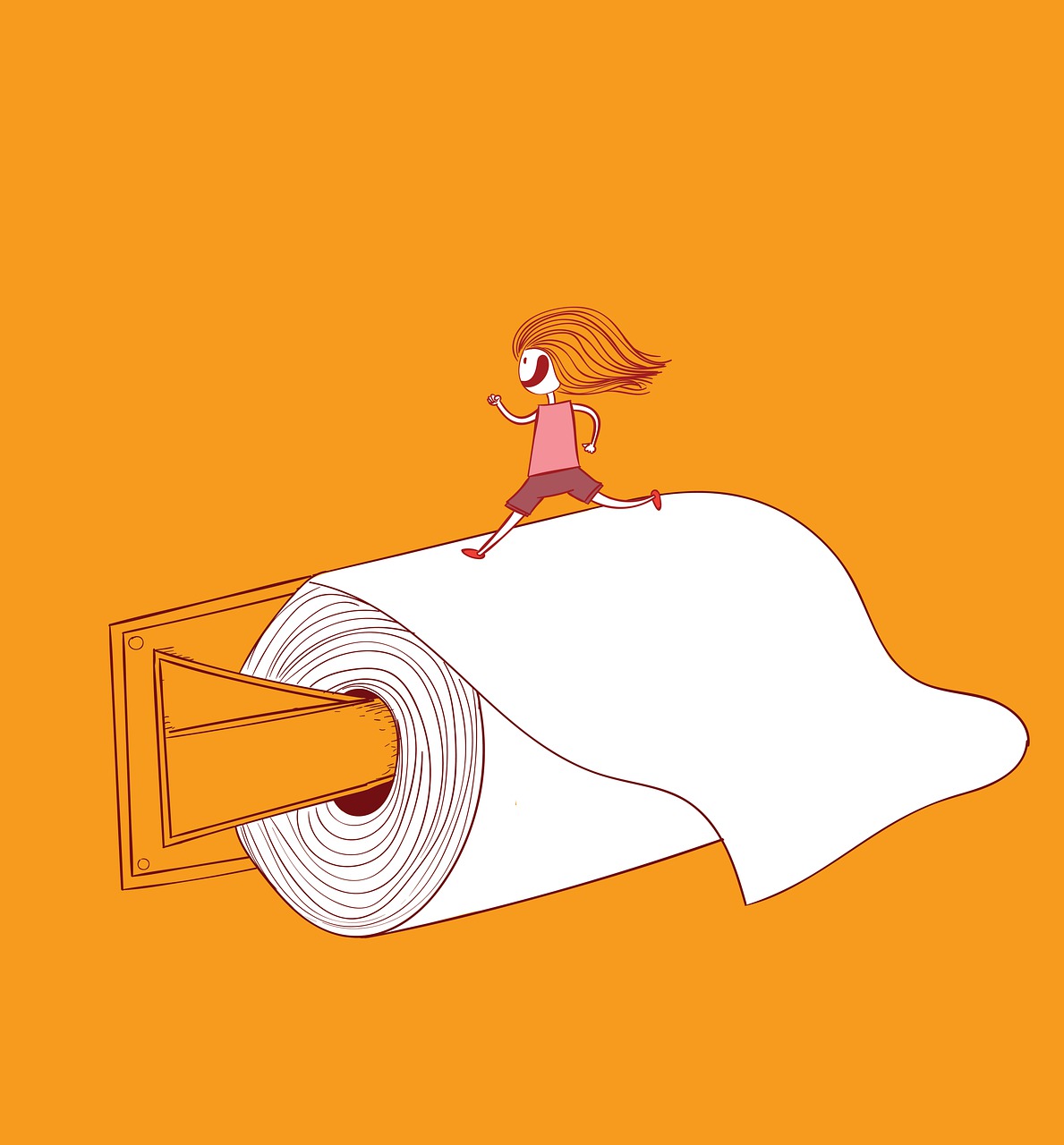★ブログの隙間をねらって、私の好きな夫の記事を載せます★
入社一年目の夏。県警に旧庁舎トイレの窓から見た夕日が目に焼き付いている。
先輩に指示された裏取を果たせず、気を利かせたつもりで幹部の部屋を回ったものの、しつこい質問に礼儀知らずと怒鳴られ、出入り禁止をくらった。
やればやるほど裏目に出る。この仕事やっていけるのか…湧きあがる不安を抑えきれず、便器の前に立ち尽くしていると、隣に立った男が声を掛けてきた。
「お疲れさん。調子はどう」ー見覚えのある顔は、事件現場で何度か見かけた中年の捜査員だった。
彼の妙な明るさに乗せられ、ダメ元で「一杯行きませんか」と誘ったら、意外にも付き合ってくれた。
未処理の書類の山に埋もれ、続発する事件を追う毎日に「子どもと付き合う時間もない」と苦笑していたが、典型的な仕事マニアなのは口ぶりで分かった。

以来、酒を酌み交わすたび敬服させられたのは、彼の物事への楽天的な姿勢だ。
最後の詰めで捜査がとん挫しても「また次がある」とくさらない。昇任試験に落ち続けても人ごとのように飄々(ヒョウヒョウ)としている。
タテ社会の壁にぶつかりながらも、自分の生きたいように生きていた。
自らの選択権を決して放棄しない生きざまは、世の中への不安を並べ立てている自分が、実はあらゆる失敗の可能性を恐れ、人生に立ちすくんでいるだけにすぎないことを気づかせてくれた。
≪2001年8月 記者の余禄≫